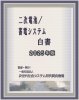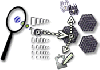■ 出版日
2006年3月
■ 価格
76,650円 (消費税込)(製本版)
■ ページ数
ページ数は備考欄をご参照下さい。
■ 発行<調査・編集>
ストラテジック・リサーチ
備考:
産学官連携白書2006年版では、報告書本体の各ページならびに総覧資料の各ページに、関連団体のホームページ、統計データ、関連レポートおよび事例解説等のインターネットページへのリンクを電子的に埋め込んであり、"e白書"という新しいスタイルで皆様にお届けしています。
乱丁・落丁以外のご返品につきましては、原則としてお申し受けできませんのでご了承ください。
レポート内容
■概要■
産学連携は、産業セクターと大学セクターを架橋し、それによって、学術研究に基礎づけられた産業を活発化し、異種融合による次世代産業活動の促進を目指す活動です。近年、関連の施策が次々と打ち出され、着実に実績をあげているものの、その多くは緒についたところであり、研究成果の帰属や還元のルール、専門人材育成など、未だ多くの課題が山積しています。
国内の各大学では、TLOの設立ラッシュや大学と民間企業との共同研究や受託研究、大学発ベンチャーなどの取り組みが本格化し、企業でも、研究開発部門の戦略見直し、大学や研究開発型企業との連携強化が求められています。
本白書は、産学官連携における多彩でダイナミックに展開する産学官連携の活動の全貌を捉え直すとともに、TLO、MOT、VC(ベンチャー・キャピタル)、産学の効果的分業、研究拠点の動向、研究予算の配分、大学発ベンチャー/ハイテクベンチャー創出、特許実務/特許戦略、知財マネジメント、知的クラスター/地域産業振興、専門人材育成等々に関する状況を網羅的に取上げ、産学官連携コーディネーション、関連コンサルティング、技術移転、プロジェクト・マネジメントなど多方面の実務で役立つよう、体系的なナレッジ・データベースとして編纂したものです。
産学官連携を体系的に編纂した本邦初の白書であり、関係諸機関、キーマン、参加企業の方々から、高い評価、多くのご賛同をいただいております。
※e白書シリーズは既に文部科学省など官庁および関連行政組織、自治体、独立行政法人、国立大学法人、公立・私立大学、各種教育・研究機関、大手・中堅・中小企業、コンサルティングファーム、シンクタンク等に多数納入実績があります。
■ 目次構成
序
================================================
【第1部】 産学連携概説
1.1 産学連携のコンセプト
1.1.1 矛盾と葛藤の緊張関係にある"産・学・官"
1.1.2 科学優位主義とリニア・モデル
1.1.4 産業政策としての産学連携
1.1.5 国の資金による産学官連携
1.1.6 民間の資金による産学官連携
1.1.7 国・地域、大学、産業のトライアングル
1.1.8 産学官連携の参加プレーヤー
1.1.9 地域と産業の連携視点
1.1.10 産業と大学の連携視点
1.1.11 地域と大学の連携視点
1.1.12 産業クラスター計画と構造改革特区
1.2 産学官連携とナショナル・イノベーション・システム
1.2.1 システムとしてのイノベーション
1.2.2 ナショナルイノベーションシステム
1.2.3 リニアモデルを超える新しいモデルとは何か
1.3 我が国の産業システムと産学連携に向けた推進政策
1.3.1 日本企業の競争・開発環境と産学官連携
1.3.2 日本の制度整備の状況と実績
1.3.3 産学官連携の実績
1.3.4 最近の産学連携施策の進捗状況
1.4 米国の産学連携
1.4.1 米国の産学連携概況
1.4.2 共同研究センター
1.4.3 バイ・ドール法制定以降の展開
1.5 欧州における産学連携の取り組みと成果
1.5.1 英国
1.5.2 ドイツ
1.5.3 スウェーデン
1.6 アジアで活発化する産学連携の動き
1.6.1 中国
1.6.2 韓国
1.6.3 その他アジア諸国における産学官連携の取り組み
1.7 わが国の産学連携
1.7.1 産学連携の概況・近況
1.7.2 産学連携を推進するための施策状況
1.7.3 埋もれる大学の知的資源
1.7.4 わが国の産学研究協力体制
================================================
【第2部】 産学連携施策、連携事業、関連制度
2.1 産学連携振興施策の状況
2.2 知財立国戦略と産学連携
2.2.1 知的財産戦略大綱
2.2.2 知的財産戦略本部
2.3 プロパテント政策と産学連携
2.3.1 科学技術創造立国の実現と産学連携
2.3.2 知的財産権の保護
2.4 各種産学連携補助事業
2.4.1 科学技術振興事業団
2.4.2 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
2.4.3 産業技術実用化開発補助事業
2.4.4 研究開発に係る情報化推進・情報基盤整備
2.5 調査報告書/答申・提言/解説文書公表
2.5.1 経産省「平成17年度大学発ベンチャーの
成長支援に関する調査報告書」
2.5.2 経団連「先端技術融合型COE」の提案
2.5.3 経産省産業構造審議会「科学技術政策の府省連携」に関する提案
2.5.4 総合科学技術会議「第三期科学技術計画」の答申
2.5.5 経団連「産学官連携によるイノベーション創出に向けた産業界の見解」
2.5.6 特許庁知的財産政策関連の概要を公表
================================================
【第3部】 産学連携関連法制度
3.1 科学技術基本法
3.2 国立大学法人法案関連6法案
3.2.1 国立大学法人法案
3.2.2 独立行政法人国立高等専門学校機構法案
3.2.3 独立行政法人大学評価・学位授与機構法案
3.2.4 独立行政法人国立大学財務・経営センター法案
3.2.5 独立行政法人メディア教育開発センター法案
3.2.6 国立大学法人等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
3.3 産学連携を対象とした諸制度および規制緩和
3.3.1 産業活力再生特別措置法
3.3.2 産業技術強化法
3.4 不正競争防止法
3.5 大学共同利用機関法人
3.5.1 人間文化研究機構
3.5.2 情報・システム研究機構
3.5.3 自然科学研究機構
3.5.4 高エネルギー加速器研究機構
================================================
【第4部】 産学連携による研究活性化策
4.1 共同研究(民間との共同研究)
4.1.1 共同研究
4.1.2 寄附金
4.1.3 税制上の優遇措置
4.1.4 共同研究センター
4.1.5 受託研究
4.2 産学連携研究活性化補助制度
4.2.1 科学研究費(科研費)
4.2.2 研究成果公開促進費
4.2.3 学術創成研究費
4.2.4 COE形成基礎研究費
4.2.5 特別研究員奨励費
4.2.6 奨学寄付金
4.2.7 研究成果最適移転事業
4.3 海外交流、外国人招聘制度関連
4.3.1 海外特別研究員制度
4.3.2 外国人招聘研究者
4.3.3 外国人著名研究者招聘事業
================================================
【第5部】 分野別プロジェクト状況、各種事例分析
5.1 産学連携の主役としての分野横断的な先端技術
5.2 ナノテクノロジー・MEMS・新材料分野
5.2.1 ナノテクノロジー・MEMS・新材料分野の概況・近況
5.2.2 省庁別のナノテクノロジー予算、重点施策、推進事業
5.2.3 日本経団連による提言
5.3 バイオ・医療分野
5.3.1 バイオナノテクノロジー/ナノバイオテクノロジー概説
5.3.2 バイオ分野の特性と産学連携
5.3.3 研究分野別動向
5.3.4 バイオインフォマティクス
5.3.5 バイオセンサーとバイオインフォマティクス
5.3.6 ナノテクノロジーと医療の地殻変動
5.3.7 ティッシュエンジニアリングと再生医療
5.3.8 ナノマシンの医療応用で見る問題点
5.3.9 バイオ業界
5.3.10 医療・医薬業界
5.3.11 主要各社の状況
5.3.12 バイオテクノロジーと産学連携
5.4 環境・エネルギー分野
5.4.1 クリーンエネルギーの現状
5.4.2 燃料電池
5.4.2.1 包新炭素材料利用の燃料電池
5.4.3 関連研究グループ
5.5 太陽電池
5.5.1 進む太陽電池の実用化と今後の課題
5.5.1.1 太陽電池の現状
5.5.1.2 次世代太陽電池に向けた開発状況
5.6 環境ケミカルサイエンス、環境リスクアセスメントの要請
5.6.1 科学技術の根本精神を揺るがしかねない危機感
5.6.2 微量元素のスペシエーション分析
5.6.3 ピコテクノロジーとしての環境分析
5.7 産学の協力が求められる化学物質の安全性評価
5.7.1 化学物質のリスクアセスメント
5.7.2 化学物質によるエコシステムへの影響とリスクアセスメント
5.7.3 トキシコゲノミクス、プロテオミクスなどの学際的協調
5.8 エレクトロニクス・電気関連分野
5.8.1 エレクトロニクス・電気関連分野概況
5.8.2 次世代ITインフラを支えるナノエレクトロニクス
5.8.3 電子デバイスとナノテク
5.8.4 次世代メモリ・記憶デバイス、MRAM
5.9 通信・IT・情報サービス分野
5.9.1 世界最先端を突き進む日本の量子暗号通信
5.9.2 注目を集めるフォトニック結晶
5.9.3 加速するモバイル機器の省エネ、小型化の動き
5.10 ロボット分野
5.10.1 ロボット分野概況
================================================
【第6部】 産学連携特区、産学連携機関による地域産業支援
6.1 産学連携特区の状況
6.1.1 構造改革特区の提案、認定等の状況
6.1.1.1 特区制度の概要
6.1.1.2 特区制度のこれまでの経緯
6.1.1.3 特区の類型
6.1.1.4 民間事業者の参入アプローチ
6.1.2 新しい連携を模索する「地域」と「大学」
6.1.2.1 これまでの経過
6.1.2.2 新しいコラボレーションの形
6.2 地域プラットフォーム活動
6.2.1 香川県
6.2.2 北九州
6.2.3 京都市
6.2.4 三重県
6.2.5 長崎県
6.3 新産業クラスター形成事業
6.3.1 知的クラスター構想
6.3.2 札幌クラスター
6.3.3 仙台クラスター
6.3.4 長野・上田クラスター
6.3.5 浜松クラスター
6.3.6 京都クラスター
6.3.7 学研クラスター
6.3.8 彩都バイオメディカルクラスター
6.3.9 関西広域クラスター
6.3.10 広島クラスター
6.3.11 香川クラスター
6.3.12 九州広域クラスター(北九州)
6.3.13 九州広域クラスター(福岡)
================================================
【第7部】 産学連携研究員制度、研究助成制度、研究交流制度
7.1 科学技術関係人材の養成
7.1.1 産学連携の視点からの科学技術関係人材の養成
7.2 研究員制度
7.2.1 特別研究員制度
7.2.2 海外特別研究員制度
7.3 科学研究費補助金
7.3.1 科学研究費
7.3.2 研究組織及び研究費の管理
7.3.3 研究成果公開促進費
7.3.4 内地研究員
7.3.5 在外研究員
7.3.6 海外研究開発動向調査等に係る研究者の派遣
7.3.7 国際研究集会派遣研究員
7.3.8 日本学術振興会関係の研究員制度
7.3.9 受託研究員
7.3.10 私学研修員、専修学校研修員及び公立学校研修員
7.3.11 産業教育内地留学生
================================================
【第8部】 産学連携研究者の養成、人材育成評価推進事業
8.1 研究者等の養成/技術人材の育成
8.1.1 イノベーションを担う起業家・経営人材の養成
8.1.2 技術経営プログラムの強化
8.1.3 実務的・実践的重視の人材育成
8.2 産学連携と高度職業人養成
8.2.1 人材育成の必要性
================================================
【第9部】 TLO、企業への技術移転の状況
9.1 TLOの現状
9.1.1 TLOの役割
9.1.2 TLOの多様な展開
9.1.3 ヨーロッパ地域のTLO活動
9.1.4 その他地域のTLO活動
9.2 TLOモデルとマッチングパターン
9.2.1 シーズとニーズのマッチング
9.2.2 技術移転が盛んな分野
9.2.2.1 IT分野
9.2.2.2 バイオ分野
9.2.2.3 電子・機械分野
9.2.3 大学の技術移転の使命
9.2.3.1 「知的財産」の確立
9.2.3.2 透明性の確保
9.2.3.3 大学法人化と技術移転
9.2.3.4 技術移転を成熟させていくには
9.2.4 TLO設置の広がり
9.2.4.1 なぜTLOが必要とされるのか
9.3 TLOと大学との連携に係る類型整理
9.3.1 業務効率に関する各類型の評価
9.3.2 利益相反と兼業規定
================================================
【第10部】 産学連携と大学改革
10.1 社会と大学が支えあう時代
10.1.1 大学のガバナンス改革から見た制度改革についての判断
10.1.2 国立大学の法人化と産学官連携
10.2 産学連携施策の一環としてのMOT(技術経営)
10.2.1 技術経営
10.2.2 技術経営のパラダイム転換
10.2.3 MOT人材の育成
10.2.4 MOT人材育成の現状
10.2.5 今後のMOT 人材育成のあり方
10.3 インターンシップの普及促進
10.3.1 インターンシップの現状
10.3.2 CO−OP 教育(Cooperative Education)
10.3.3 PBL(Project Based Learning)
10.3.4 TEC(Technology,
Education and Commercialization)
10.3.5 インターンシップ制度の課題
10.4 大学発ベンチャーの状況、取り組み、活動
10.4.1 NEDO「大学と企業の共同研究マッチングファンド」に
関する事業
10.4.2 筑波大学・横浜国立大学「大学発ベンチャー企業調査」
10.4.3 経済産業省産業「大学発ベンチャー企業達成率」を公表
10.5 人材育成評価推進事業(アクレディテーション)
10.5.1 アクレディテーションの現状
10.5.1.1 米国専門教育機関のアクレディテーション
10.5.2 わが国におけるアクレディテーション・システムの動向
================================================
【第11部】 産学連携の事業戦略、財務戦略、共創投資
11.1 大学におけるインキュベーション事業
11.1.1 産学連携・大学発ベンチャー創造への提言
11.2 クラスター事業における評価の確立とエクイティを活用
11.2.1 クラスター事業における評価の確立
11.2.2 知的クラスターにおけるエクイティ活用
11.3 アライアンスの一種としての産学連携
11.3.1 企業と大学のカルチャーを考慮に入れた産学連携
11.3.2 意識改革の必要性
================================================
【第12部】 産学連携のプロジェクト管理およびコーディネーション機能
12.1 プロジェクト型産学連携組織
12.2 大学が産学連携と取り組むためのフレームワーク
12.2.1 組織間の共同体制と契約管理
12.2.1.1 プロジェクト管理
12.2.1.2 知財管理
12.2.1.3 情報管理
12.3 産学連携とコーディネータ
12.3.1 産学官連携と共同研究促進のための触媒的役割
12.3.2 産学官連携におけるオーケストレーション(総合指揮)機能
================================================
【第13部】 産学連携と特許実務
13.1 特許、特許実務、特許制度の概念
13.1.1 特許と発明・発明者
13.1.2 発明・発明者
13.1.2.1 発明(特許)であるための条件
13.1.3 発明の本質と発明の上位概念化
13.2 知的財産権と特許(法)制度
13.2.1 知的財産権、産業財産権(工業所有権)、特許の関係
13.2.2 産業財産権(工業所有権)
13.2.3 審査主義および出願審査請求制度
13.2.4 審査請求および出願審査
13.2.5 実施権
13.2.6 審判・審判請求
13.2.7 訴訟
13.2.8 侵害訴訟における主要論点
13.2.9 職務発明・業務発明
13.2.10 職務発明訴訟とコンプライアンス
13.3 特許実務
13.3.1 特許明細書の作成
13.3.2 特許権の譲渡・ライセンスの算定
13.3.3 知的財産およびライセンスの管理
================================================
【第14部】 産学連携における法的問題の解決
14.1 産学官連携における法的問題概説
14.1.1 ライセンスと知財の債券化
14.1.2 特許の価値
14.1.3 ライセンス料およびライセンス契約の問題
14.1.3.1 ライセンス契約の期間
14.1.3.2 ライセンス料の契約
14.2 大学・研究者の特許戦略
14.2.1 研究の誘導体としての特許
14.2.2 不実施補償
14.2.3 ポートフォリオと特許マップ
14.2.4 特許引用ツリー
================================================
【総覧資料1】 関連団体・組織
省庁・関連主要団体
経済産業局特許室・知的所有権センター
技術移転に関するサポート機関
研究者奨学金制度関連団体
公的試験研究機関
共同研究センター
インキュベータ(インキュベータ関連機関)
================================================
【総覧資料2】 関連制度/研究補助制度
研究補助制度
産学官連携関連認定特区(35特区)
================================================
【総覧資料3】 参考文献・書籍
参考書籍・文献
白書・報告書類
論文・ジャーナル
オンライン(ダウンロード)記事/Web掲載ジャーナル
その他専門雑誌・各種研究レポート
============================================================
【総覧資料4】 関連サイト(イエローページ集)
都道府県別研究交流機関
地域共同研究センター
================================================
【総覧資料5】 学術賞・アワード総覧
================================================
2006年3月
■ 価格
76,650円 (消費税込)(製本版)
■ ページ数
ページ数は備考欄をご参照下さい。
■ 発行<調査・編集>
ストラテジック・リサーチ
備考:
産学官連携白書2006年版では、報告書本体の各ページならびに総覧資料の各ページに、関連団体のホームページ、統計データ、関連レポートおよび事例解説等のインターネットページへのリンクを電子的に埋め込んであり、"e白書"という新しいスタイルで皆様にお届けしています。
乱丁・落丁以外のご返品につきましては、原則としてお申し受けできませんのでご了承ください。
レポート内容
■概要■
産学連携は、産業セクターと大学セクターを架橋し、それによって、学術研究に基礎づけられた産業を活発化し、異種融合による次世代産業活動の促進を目指す活動です。近年、関連の施策が次々と打ち出され、着実に実績をあげているものの、その多くは緒についたところであり、研究成果の帰属や還元のルール、専門人材育成など、未だ多くの課題が山積しています。
国内の各大学では、TLOの設立ラッシュや大学と民間企業との共同研究や受託研究、大学発ベンチャーなどの取り組みが本格化し、企業でも、研究開発部門の戦略見直し、大学や研究開発型企業との連携強化が求められています。
本白書は、産学官連携における多彩でダイナミックに展開する産学官連携の活動の全貌を捉え直すとともに、TLO、MOT、VC(ベンチャー・キャピタル)、産学の効果的分業、研究拠点の動向、研究予算の配分、大学発ベンチャー/ハイテクベンチャー創出、特許実務/特許戦略、知財マネジメント、知的クラスター/地域産業振興、専門人材育成等々に関する状況を網羅的に取上げ、産学官連携コーディネーション、関連コンサルティング、技術移転、プロジェクト・マネジメントなど多方面の実務で役立つよう、体系的なナレッジ・データベースとして編纂したものです。
産学官連携を体系的に編纂した本邦初の白書であり、関係諸機関、キーマン、参加企業の方々から、高い評価、多くのご賛同をいただいております。
※e白書シリーズは既に文部科学省など官庁および関連行政組織、自治体、独立行政法人、国立大学法人、公立・私立大学、各種教育・研究機関、大手・中堅・中小企業、コンサルティングファーム、シンクタンク等に多数納入実績があります。
■ 目次構成
序
================================================
【第1部】 産学連携概説
1.1 産学連携のコンセプト
1.1.1 矛盾と葛藤の緊張関係にある"産・学・官"
1.1.2 科学優位主義とリニア・モデル
1.1.4 産業政策としての産学連携
1.1.5 国の資金による産学官連携
1.1.6 民間の資金による産学官連携
1.1.7 国・地域、大学、産業のトライアングル
1.1.8 産学官連携の参加プレーヤー
1.1.9 地域と産業の連携視点
1.1.10 産業と大学の連携視点
1.1.11 地域と大学の連携視点
1.1.12 産業クラスター計画と構造改革特区
1.2 産学官連携とナショナル・イノベーション・システム
1.2.1 システムとしてのイノベーション
1.2.2 ナショナルイノベーションシステム
1.2.3 リニアモデルを超える新しいモデルとは何か
1.3 我が国の産業システムと産学連携に向けた推進政策
1.3.1 日本企業の競争・開発環境と産学官連携
1.3.2 日本の制度整備の状況と実績
1.3.3 産学官連携の実績
1.3.4 最近の産学連携施策の進捗状況
1.4 米国の産学連携
1.4.1 米国の産学連携概況
1.4.2 共同研究センター
1.4.3 バイ・ドール法制定以降の展開
1.5 欧州における産学連携の取り組みと成果
1.5.1 英国
1.5.2 ドイツ
1.5.3 スウェーデン
1.6 アジアで活発化する産学連携の動き
1.6.1 中国
1.6.2 韓国
1.6.3 その他アジア諸国における産学官連携の取り組み
1.7 わが国の産学連携
1.7.1 産学連携の概況・近況
1.7.2 産学連携を推進するための施策状況
1.7.3 埋もれる大学の知的資源
1.7.4 わが国の産学研究協力体制
================================================
【第2部】 産学連携施策、連携事業、関連制度
2.1 産学連携振興施策の状況
2.2 知財立国戦略と産学連携
2.2.1 知的財産戦略大綱
2.2.2 知的財産戦略本部
2.3 プロパテント政策と産学連携
2.3.1 科学技術創造立国の実現と産学連携
2.3.2 知的財産権の保護
2.4 各種産学連携補助事業
2.4.1 科学技術振興事業団
2.4.2 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)
2.4.3 産業技術実用化開発補助事業
2.4.4 研究開発に係る情報化推進・情報基盤整備
2.5 調査報告書/答申・提言/解説文書公表
2.5.1 経産省「平成17年度大学発ベンチャーの
成長支援に関する調査報告書」
2.5.2 経団連「先端技術融合型COE」の提案
2.5.3 経産省産業構造審議会「科学技術政策の府省連携」に関する提案
2.5.4 総合科学技術会議「第三期科学技術計画」の答申
2.5.5 経団連「産学官連携によるイノベーション創出に向けた産業界の見解」
2.5.6 特許庁知的財産政策関連の概要を公表
================================================
【第3部】 産学連携関連法制度
3.1 科学技術基本法
3.2 国立大学法人法案関連6法案
3.2.1 国立大学法人法案
3.2.2 独立行政法人国立高等専門学校機構法案
3.2.3 独立行政法人大学評価・学位授与機構法案
3.2.4 独立行政法人国立大学財務・経営センター法案
3.2.5 独立行政法人メディア教育開発センター法案
3.2.6 国立大学法人等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
3.3 産学連携を対象とした諸制度および規制緩和
3.3.1 産業活力再生特別措置法
3.3.2 産業技術強化法
3.4 不正競争防止法
3.5 大学共同利用機関法人
3.5.1 人間文化研究機構
3.5.2 情報・システム研究機構
3.5.3 自然科学研究機構
3.5.4 高エネルギー加速器研究機構
================================================
【第4部】 産学連携による研究活性化策
4.1 共同研究(民間との共同研究)
4.1.1 共同研究
4.1.2 寄附金
4.1.3 税制上の優遇措置
4.1.4 共同研究センター
4.1.5 受託研究
4.2 産学連携研究活性化補助制度
4.2.1 科学研究費(科研費)
4.2.2 研究成果公開促進費
4.2.3 学術創成研究費
4.2.4 COE形成基礎研究費
4.2.5 特別研究員奨励費
4.2.6 奨学寄付金
4.2.7 研究成果最適移転事業
4.3 海外交流、外国人招聘制度関連
4.3.1 海外特別研究員制度
4.3.2 外国人招聘研究者
4.3.3 外国人著名研究者招聘事業
================================================
【第5部】 分野別プロジェクト状況、各種事例分析
5.1 産学連携の主役としての分野横断的な先端技術
5.2 ナノテクノロジー・MEMS・新材料分野
5.2.1 ナノテクノロジー・MEMS・新材料分野の概況・近況
5.2.2 省庁別のナノテクノロジー予算、重点施策、推進事業
5.2.3 日本経団連による提言
5.3 バイオ・医療分野
5.3.1 バイオナノテクノロジー/ナノバイオテクノロジー概説
5.3.2 バイオ分野の特性と産学連携
5.3.3 研究分野別動向
5.3.4 バイオインフォマティクス
5.3.5 バイオセンサーとバイオインフォマティクス
5.3.6 ナノテクノロジーと医療の地殻変動
5.3.7 ティッシュエンジニアリングと再生医療
5.3.8 ナノマシンの医療応用で見る問題点
5.3.9 バイオ業界
5.3.10 医療・医薬業界
5.3.11 主要各社の状況
5.3.12 バイオテクノロジーと産学連携
5.4 環境・エネルギー分野
5.4.1 クリーンエネルギーの現状
5.4.2 燃料電池
5.4.2.1 包新炭素材料利用の燃料電池
5.4.3 関連研究グループ
5.5 太陽電池
5.5.1 進む太陽電池の実用化と今後の課題
5.5.1.1 太陽電池の現状
5.5.1.2 次世代太陽電池に向けた開発状況
5.6 環境ケミカルサイエンス、環境リスクアセスメントの要請
5.6.1 科学技術の根本精神を揺るがしかねない危機感
5.6.2 微量元素のスペシエーション分析
5.6.3 ピコテクノロジーとしての環境分析
5.7 産学の協力が求められる化学物質の安全性評価
5.7.1 化学物質のリスクアセスメント
5.7.2 化学物質によるエコシステムへの影響とリスクアセスメント
5.7.3 トキシコゲノミクス、プロテオミクスなどの学際的協調
5.8 エレクトロニクス・電気関連分野
5.8.1 エレクトロニクス・電気関連分野概況
5.8.2 次世代ITインフラを支えるナノエレクトロニクス
5.8.3 電子デバイスとナノテク
5.8.4 次世代メモリ・記憶デバイス、MRAM
5.9 通信・IT・情報サービス分野
5.9.1 世界最先端を突き進む日本の量子暗号通信
5.9.2 注目を集めるフォトニック結晶
5.9.3 加速するモバイル機器の省エネ、小型化の動き
5.10 ロボット分野
5.10.1 ロボット分野概況
================================================
【第6部】 産学連携特区、産学連携機関による地域産業支援
6.1 産学連携特区の状況
6.1.1 構造改革特区の提案、認定等の状況
6.1.1.1 特区制度の概要
6.1.1.2 特区制度のこれまでの経緯
6.1.1.3 特区の類型
6.1.1.4 民間事業者の参入アプローチ
6.1.2 新しい連携を模索する「地域」と「大学」
6.1.2.1 これまでの経過
6.1.2.2 新しいコラボレーションの形
6.2 地域プラットフォーム活動
6.2.1 香川県
6.2.2 北九州
6.2.3 京都市
6.2.4 三重県
6.2.5 長崎県
6.3 新産業クラスター形成事業
6.3.1 知的クラスター構想
6.3.2 札幌クラスター
6.3.3 仙台クラスター
6.3.4 長野・上田クラスター
6.3.5 浜松クラスター
6.3.6 京都クラスター
6.3.7 学研クラスター
6.3.8 彩都バイオメディカルクラスター
6.3.9 関西広域クラスター
6.3.10 広島クラスター
6.3.11 香川クラスター
6.3.12 九州広域クラスター(北九州)
6.3.13 九州広域クラスター(福岡)
================================================
【第7部】 産学連携研究員制度、研究助成制度、研究交流制度
7.1 科学技術関係人材の養成
7.1.1 産学連携の視点からの科学技術関係人材の養成
7.2 研究員制度
7.2.1 特別研究員制度
7.2.2 海外特別研究員制度
7.3 科学研究費補助金
7.3.1 科学研究費
7.3.2 研究組織及び研究費の管理
7.3.3 研究成果公開促進費
7.3.4 内地研究員
7.3.5 在外研究員
7.3.6 海外研究開発動向調査等に係る研究者の派遣
7.3.7 国際研究集会派遣研究員
7.3.8 日本学術振興会関係の研究員制度
7.3.9 受託研究員
7.3.10 私学研修員、専修学校研修員及び公立学校研修員
7.3.11 産業教育内地留学生
================================================
【第8部】 産学連携研究者の養成、人材育成評価推進事業
8.1 研究者等の養成/技術人材の育成
8.1.1 イノベーションを担う起業家・経営人材の養成
8.1.2 技術経営プログラムの強化
8.1.3 実務的・実践的重視の人材育成
8.2 産学連携と高度職業人養成
8.2.1 人材育成の必要性
================================================
【第9部】 TLO、企業への技術移転の状況
9.1 TLOの現状
9.1.1 TLOの役割
9.1.2 TLOの多様な展開
9.1.3 ヨーロッパ地域のTLO活動
9.1.4 その他地域のTLO活動
9.2 TLOモデルとマッチングパターン
9.2.1 シーズとニーズのマッチング
9.2.2 技術移転が盛んな分野
9.2.2.1 IT分野
9.2.2.2 バイオ分野
9.2.2.3 電子・機械分野
9.2.3 大学の技術移転の使命
9.2.3.1 「知的財産」の確立
9.2.3.2 透明性の確保
9.2.3.3 大学法人化と技術移転
9.2.3.4 技術移転を成熟させていくには
9.2.4 TLO設置の広がり
9.2.4.1 なぜTLOが必要とされるのか
9.3 TLOと大学との連携に係る類型整理
9.3.1 業務効率に関する各類型の評価
9.3.2 利益相反と兼業規定
================================================
【第10部】 産学連携と大学改革
10.1 社会と大学が支えあう時代
10.1.1 大学のガバナンス改革から見た制度改革についての判断
10.1.2 国立大学の法人化と産学官連携
10.2 産学連携施策の一環としてのMOT(技術経営)
10.2.1 技術経営
10.2.2 技術経営のパラダイム転換
10.2.3 MOT人材の育成
10.2.4 MOT人材育成の現状
10.2.5 今後のMOT 人材育成のあり方
10.3 インターンシップの普及促進
10.3.1 インターンシップの現状
10.3.2 CO−OP 教育(Cooperative Education)
10.3.3 PBL(Project Based Learning)
10.3.4 TEC(Technology,
Education and Commercialization)
10.3.5 インターンシップ制度の課題
10.4 大学発ベンチャーの状況、取り組み、活動
10.4.1 NEDO「大学と企業の共同研究マッチングファンド」に
関する事業
10.4.2 筑波大学・横浜国立大学「大学発ベンチャー企業調査」
10.4.3 経済産業省産業「大学発ベンチャー企業達成率」を公表
10.5 人材育成評価推進事業(アクレディテーション)
10.5.1 アクレディテーションの現状
10.5.1.1 米国専門教育機関のアクレディテーション
10.5.2 わが国におけるアクレディテーション・システムの動向
================================================
【第11部】 産学連携の事業戦略、財務戦略、共創投資
11.1 大学におけるインキュベーション事業
11.1.1 産学連携・大学発ベンチャー創造への提言
11.2 クラスター事業における評価の確立とエクイティを活用
11.2.1 クラスター事業における評価の確立
11.2.2 知的クラスターにおけるエクイティ活用
11.3 アライアンスの一種としての産学連携
11.3.1 企業と大学のカルチャーを考慮に入れた産学連携
11.3.2 意識改革の必要性
================================================
【第12部】 産学連携のプロジェクト管理およびコーディネーション機能
12.1 プロジェクト型産学連携組織
12.2 大学が産学連携と取り組むためのフレームワーク
12.2.1 組織間の共同体制と契約管理
12.2.1.1 プロジェクト管理
12.2.1.2 知財管理
12.2.1.3 情報管理
12.3 産学連携とコーディネータ
12.3.1 産学官連携と共同研究促進のための触媒的役割
12.3.2 産学官連携におけるオーケストレーション(総合指揮)機能
================================================
【第13部】 産学連携と特許実務
13.1 特許、特許実務、特許制度の概念
13.1.1 特許と発明・発明者
13.1.2 発明・発明者
13.1.2.1 発明(特許)であるための条件
13.1.3 発明の本質と発明の上位概念化
13.2 知的財産権と特許(法)制度
13.2.1 知的財産権、産業財産権(工業所有権)、特許の関係
13.2.2 産業財産権(工業所有権)
13.2.3 審査主義および出願審査請求制度
13.2.4 審査請求および出願審査
13.2.5 実施権
13.2.6 審判・審判請求
13.2.7 訴訟
13.2.8 侵害訴訟における主要論点
13.2.9 職務発明・業務発明
13.2.10 職務発明訴訟とコンプライアンス
13.3 特許実務
13.3.1 特許明細書の作成
13.3.2 特許権の譲渡・ライセンスの算定
13.3.3 知的財産およびライセンスの管理
================================================
【第14部】 産学連携における法的問題の解決
14.1 産学官連携における法的問題概説
14.1.1 ライセンスと知財の債券化
14.1.2 特許の価値
14.1.3 ライセンス料およびライセンス契約の問題
14.1.3.1 ライセンス契約の期間
14.1.3.2 ライセンス料の契約
14.2 大学・研究者の特許戦略
14.2.1 研究の誘導体としての特許
14.2.2 不実施補償
14.2.3 ポートフォリオと特許マップ
14.2.4 特許引用ツリー
================================================
【総覧資料1】 関連団体・組織
省庁・関連主要団体
経済産業局特許室・知的所有権センター
技術移転に関するサポート機関
研究者奨学金制度関連団体
公的試験研究機関
共同研究センター
インキュベータ(インキュベータ関連機関)
================================================
【総覧資料2】 関連制度/研究補助制度
研究補助制度
産学官連携関連認定特区(35特区)
================================================
【総覧資料3】 参考文献・書籍
参考書籍・文献
白書・報告書類
論文・ジャーナル
オンライン(ダウンロード)記事/Web掲載ジャーナル
その他専門雑誌・各種研究レポート
============================================================
【総覧資料4】 関連サイト(イエローページ集)
都道府県別研究交流機関
地域共同研究センター
================================================
【総覧資料5】 学術賞・アワード総覧
================================================